スタッフブログ
2019/02/15
三都セミナー②
なぜヨーロッパは、木造建築に向かっているのでしょう?
それは、木造こそ究極の「サスティナビリティ」だからです。
日本人にとって「木」は身近な存在ですが、実に大事な生物でも有ります。
2000年、あるいはそれ以上も前から、巨木を利用して神殿や櫓を作り、家を構築してきました。(川内丸山遺跡、古出雲大社、吉野ケ里遺跡など)
人口が1億人を超える国で、国土の3分の1(67%)が森林、そのまた3ぶんの1が植林による人工林などという国は、世界中を探しても日本だけです。
人工林の技術は、500年前に遡る室町時代末期と言われています。
長い歴史のあるヨーロッパの石の文化、エジプトからギリシャローマを経て
現在のパリの街並みやイタリア、ドイツの大聖堂等々、それらは皆石造りです。
それが、近年劇的に変化してきました。
冷たい石の家に暮らし、薪をくべて温める生活から、木の家を建て僅かな熱源で温まる省エネな生活にすることが、大切になってきたのです。
10階建てのビルまでもが、木造化をされています。
石の家ばかり作ってきたフランスでも、木造住宅を建てると国が補助金を出します。
建築素材としての木造の良さ(エコロジー&エコノミー)にようやく気が付いたのでしょう。
日本人は、家づくりに最初から“木”を選びました。
大理石こそ有りませんが、日本にも御影石(グラニット)は有ります。
にもかかわらず、木を選び、神殿を建て、住まいを建てました。
そして、500年前といえば日本人の人口はせいぜい2500万人(江戸時代初期3000万人)
その時代には、森林率が80%以上だったと思われます。(現在67%)
いくらでもある木を、切ったら植える植林と、枝払いや間引きをする育林技術を育てていった先人達の知恵に感服します。
今風に言えば、木材開発イノベーションとも言えそうです。
話は飛びますが、その木材を使った断熱材が、ドイツで開発され、今後世界の木造住宅の外断熱材としての必須アイテムとなりそうです。
そして、その外断熱という概念を日本に初めて紹介した田中先生を、ドイツから日本に呼び戻した人物が先頃お亡くなりになりました。













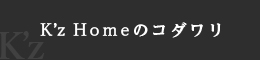










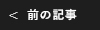
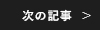
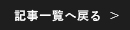



 0569-25-0017
0569-25-0017